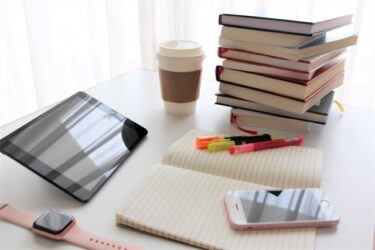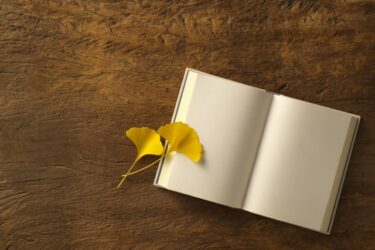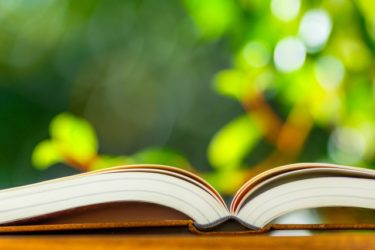こんにちは!さくらピクニックです(経歴など気になるかたはこちら)。
この「東大受験体験記ブログ」カテゴリでは、その名の通り私自身の受験体験の記憶を、だいたいの時系列で長々と記事にしています。
基本的には「私はこうしたよ」というスタンスで書いています。
また、受験は数年前のことになるので、覚えていないことや、今とは少し違うこともあると思います。
(「こうするのがオススメ」というのは「勉強のお悩み改善」カテゴリでたくさん触れていますので、よければぜひ!)
今回は、高校2年の時の勉強や、塾選びのこと、勉強法を勉強していたことについて語っていきます!
高2の秋冬
高2の後半から、高校でもなんとなく受験の雰囲気が出てきており、受験をより意識するようになりました。
塾選び
高2の冬に、塾を変えました。
もともと塾でそこまで講座をとったり授業を受けまくったりはしていませんでしたが、勉強のサポートはしてもらえますし、自習室が夜や休日でも使えることもあり通っていました。(通わせてもらっていました。)
はじめに通っていたのがローカルな少人数授業の塾で、そこから河合塾マナビスに変えました。
(ちょうど良い田舎なので大手予備校は映像授業が基本でした。)
こんにちは!さくらピクニックです。(経歴などはこちら。) 私は大学受験の際、 河合塾マナビスという塾に通っていました。 この記事では、 「マナビスって実際どうなの?」 という[…]
辞めるのも新しいところに入るのもエネルギーや時間が要るので、変えるときにとても悩んで決断したのですが、私のなかでこの決断がかなり(良い意味で)ポイントになったと思っています。
変えて本当に良かったと思っています。
変える決断をする上で決め手となったのは、
・塾(自習室)が綺麗で、家と学校から近くなる
・授業の質や形式が、「大学受験に向けて」という視点では良さそう
ということです。
こんにちは!さくらピクニックです。(経歴などはこちら。) この記事では、中高大と、実際にたくさんの塾に通った私自身の経験をもとに、 そもそも塾は必要か?「塾に行かない方がいい」こともある? なぜ[…]
通いやすさと過ごしやすさ
家や学校から近い、というのは個人的にとても大切でした。
近くなると、学校帰りや休日に気が向いたらすぐ行ける、習慣的に通いやすい、ということにより集中して勉強できる時間が増えたと感じました。
また、単純に建物や部屋が綺麗で快適でした。
高3になるとほぼ休まず毎日自習室に通っていたので、環境と近さの点では圧倒的に「変えて良かった」です。
↓の記事で勉強する環境について触れています!
授業の質
授業の質は簡単に測ることができませんが、映像授業では都会の(?)予備校の講師陣の授業を受けられること、大学別の過去問対策がしっかりしていることがメリットに見えました。
その前通っていた塾は地元にしかない塾で、少人数とはいえ集団授業がメインだったので、いろいろな志望校の人と授業を受けていました。
理解度を見てもらいながらじっくり進められるという点や、学校の試験対策や模試対策という点ではこちらの方が良かったのかもしれません。
(少なくとも通っていた時は…の話でしかないですが。)
しかし、大学受験に向けて本格的に動き出そうとしているときによく考えた結果、自分のペースで勉強を進められて、大学別の対策がしっかりしている方が自分には合っていると思い、決断しました。
そこまでお金を掛けたくなかったので、苦手な数学を中心に授業をとり、過去問講座は国語以外をとる、という感じだったはずです。
なので、自習室で自習している時間の方が圧倒的に多かったと思います。
(良い校舎長だったのか、授業をもっと取るように言われることはほとんどありませんでした。)
自習の計画を立ててもらえるわけではないので、(塾の講座でなく)自分で勉強する分は自分で色々調べ、考えて勉強していました。
勉強法の勉強
つい先程の文章と被ってしまいますが、塾ではそこまで多く授業をとっておらず、自習の計画を立ててもらえるわけでもありませんでした。
勉強するなら志望校に合格したいですし、そのためにも少しでも効率的・効果的にやりたいですよね。
ということで、私は勉強法を勉強していました。高2の冬くらいがそのピークだったと思います。
情報収集先として、もちろん友達や学校の先生などから教わること、ネットで調べることも多かったですが、勉強法に関する本を探して読んでいました。
もちろん自分の勉強計画を立てたり、勉強法を学んだりするためにやっていたのですが、サクセスストーリー仕立てになっているものなどや普通に読んでいて面白かったですし、いろいろな勉強方法で効果がありそうなものを見つけるとワクワクしました。
そして読んでいるだけで不思議と勉強したくなりました。
たくさん読みましたが、すぐ忘れて身についていないものもとても多かったです。
しかし、全てを真似る必要もない気がしますし、少しでも自分に合った方法が見つかったり、モチベーションになったりすれば良い、とも思います。
一応、記憶に残っているものをいくつか紹介してみようと思います。
注意?
こういう勉強法の本は、本当にたくさんあります。
また、実際に勉強して知識やできることを積み重ねていかないと、勉強法を知っただけでは成績は伸びません(よね…?)。
私は「勉強法の勉強」は「やって良かった」と思っていますが、そればかりにはなりすぎないように適度に、ということを注意する必要があるかもしれません。
ですので残された時間なども確認して、気になる方は覗いてみてください。
読んでいた勉強法の本ピックアップ
特に「最新脳科学が教える 高校生の勉強法」というのが個人的には好きで、今でも内容を思い出すことがあります。
高校生の勉強法、と書かれていますが、高校以降も応用できるものが多いと思います。
著者は東大の先生だったと思います。
「受験の叡智」は、非常に詳しく勉強内容・方法まで書かれていたはずです。
共通テストに対応した新しいバージョンが出ていたので、そちらのリンクを載せておきます。
最後のこの本は、ストーリー感が他のものよりも強めで、少し「ビリギャル」に似ているかもしれません。
自分の受験勉強や今後の「勉強」そのものについて、役立つようなことも多く書かれていたと記憶しています。
(「ビリギャル」も映画を見ました!面白かったです。)
まとめ
今回は高2の時の塾選び、勉強法を勉強していた(?)話について記事にしていきました!
次回は高3での習慣づけの話をしようと思います。合わせてご覧いただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!お役に立てればとても嬉しいです。
ご相談やご質問なども「お問い合わせ」にて受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。(原則として内容や情報が公開されることはありません。)
できる範囲でお答えします。